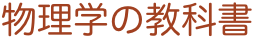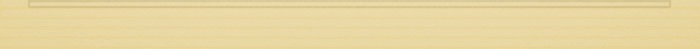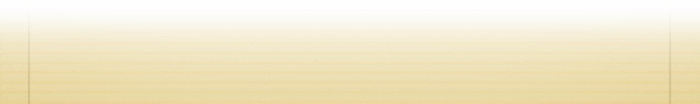物理を学ぶにはじっくり教科書を読むのがよい。現代は教科書がありふれていて何を読んだらいいか迷ってしまう。物理は数学ほどではないが,時代によって内容が変わることがほとんどないので,古い本でも構わない。たとえば,高校で教えている物理は全て19世紀までの物理である。むしろ古い本のほうが,臨場感が伝わっていて素晴らしいこともある。ここでは,私が今まで読んできた物理の教科書の中で印象に残った本を思い出を交えながら紹介する。記憶だけで書いているので間違っていることもあるかもしれない。
物理学一般
ファインマン物理学
大学に合格したときに高校の物理の先生のところに行ったときに紹介された本。大学に入ってすぐに「力学」を買って読みはじめた。赤いハードカバーの大きな本。ファインマンがカルテクで,大学の1,2年生相手にたったの1回だけ行った講義らしい。1週間に2回の講義と1回の演習が行われ,原書で3冊,日本語訳で5冊にもなる。全講義数は120回(1回90分)で,演習は60回になる。これに対応して,私が教養部のときに受けた物理の講義は45回で,演習はなかった。アメリカにはかなわないなとつくづく思った記憶がある。
この教科書は講義を本にしているからだろうか,ファインマンの講義の臨場感を感じる。読んでいて非常に楽しく感じるのはファインマンが本当に物理を楽しんでいるからであろう。ただし,決して簡単な本ではない。むしろ危険な本である。もし,この教科書を完全に理解したとすれば,研究者として必要な物理の考え方は十分であると思う。何もない山奥のような静かなところに行って,心静かに読んでみたい本である。定年後はいいかもしれない。
物理学を本にして説明することが難しいことはいつも感じている。物理学は自然科学であり何かの本に書かれたものではないので,本にすることで情報量は一気に落ちる。いつも学生に「モナリザの絵を見ずにモナリザを説明しているようなもの」と話している。ファインマンは物理学を語るのに数式でごまかすのではなく,数式の本当の意味を言葉で語り,まさに絵を見ずにどこまで絵を説明できるかに挑戦したものであると言える。そしてそれは,私が想像しうる最高の説明なのである。話そのものは高校生でもある程度優秀であれば丁寧に読めばわかるであろうが,その真の意味は初学者にはまずわからない超高級なことである。ファインマン物理学全5巻を通じてのファインマンの筋は一本であり,それを理解できれば「絵」が浮かび上がってくることであろう。
私自身は物理の本当の美しさを完全に知り尽くしてるわけではない(というかその入り口にも入っていないかもしれない)が,物理は美しくて楽しいということは良く知っているし,学生たちにも講義や研究を通じて物理の世界の素晴らしさを伝えることが生き甲斐である。ファインマン物理学を読んでいると,そういう気持ちだけは似ているのかなと思う(物理学者としての格は全然違うが)。
それにしても驚くのはこれだけの講義を準備したファインマンの力量である。なんと,最近全文がWebで読めるようになった。出版から50年経っても書店で手にはいるというすごい本。
ランダウ=リフシッツ理論物理学教程
大学に入学すると同時に「理論物理研究会」というサークルに入り,毎日物理の勉強に没頭した。そのときに先輩から薦められたのが,この教程。とりあえず力学を購入して読み始めたが,これが難しい。力学なのにニュートンの法則から始まらずに,いきなり一般化座標から入り,すぐに最小作用の原理が出てくる。「なんだこりゃ」という感じであった。1ページ読むのに1日かかるという大変な本であったが,大学のすごさに触れた思いがして必死に読んだ。この教程はファインマンと違って無駄なことは一切書かれていない。短い言葉に物理の本質が凝縮されており天才ランダウのすごさを感じる。この教程を全部理解したとすれば,世界一流の物理学者と対等に渡り合えることであろう。ただ残念なことに,ほとんど絶版になってしまっている。幸いなことに私はほとんど持っている(ほとんど読んでいないが)。なんと,旧版であるがランダウ=リフシッツ理論物理学教程が無料でdownload (Mechanics)できる。その他の巻もほとんどがこのサイトで検索すればみつかるし,下で紹介するシッフの量子力学もある。しかし,どう考えても書籍をスキャンしたものであり,出版社が出しているとは思えない。昔の海賊版みたいなものかもしれない。要注意である。
バークレー物理学コース
この本はファインマン物理学と同じ頃,アメリカのバークレーで物理学者を育成するためのコースとして,ノーベル賞クラスの一流の物理学者が書いた本である。このシリーズがいい本だというのは知っていたのであるが,力学の最初を買って読み始めたときに,あまりにも簡単なので拍子抜けしてしまって読むのをやめてしまった。アメリカの高校の物理のレベルは日本と比べて低いために易しいところから始めるからであろうがゴールは非常に高い。数年前に電磁気学を読んだが,これには圧倒されてしまった。特に5章。誰が書いたのかと思って著者を見るとNMRを開発したPurcellだという。ノーベル賞学者である。この本を訳した方は飯田修一先生で脚注が面白い。普通脚注は本の理解のために書くものであるが,そこには飯田物理学が顔を出してPurcellに対する批判みたいなことも書かれていたりして,苦笑いしながら読んでしまう。2版ではその脚注が激減しているが,それは強い圧力がかかったためらしい。飯田先生の物理に関してはコメントできる立場ではないが,先生の精神力の強さには脱帽するばかりである。少し前に先生が老衰でなくなったという話を知ったときは本当に残念だと思った。
物理学への道
この本は大学の教養課程の物理で使っていた本であるが,実に良く出来ている。この本が出来たいきさつは序文に書いてあり,アメリカではファインマン物理学やバークレー物理学コースなどの良い教科書があり,それによる教育が成功しているが,日本ではそのような良書はない。それならば,ファインマンやバークレーを使えばいいのではないか,ということになるが,残念ながらアメリカと日本の高校で学ぶ物理は非常に異なっているために,そのまま使うことは出来ない。そこで当時の大阪大学教養部の一流の先生方が結集して,日本版のファインマンあるいはバークレーを目指したとのことである。そのうたい文句通りに,この本は素晴らしい。この本の特徴は数式を羅列するだけでなく,物理学の歴史やその考え方を丁寧にたどりながらとびがなく進めていくところにある。丁寧に読めば必ずわかる本で,日本人に合っていると思う。残念なことに絶版となってしまった。
量子力学
シッフ「量子力学」
これは学部のときの量子力学の参考書。量子力学の講義は湯川秀樹の助手だった田中一先生。そのせいか哲学的な話が多く,教科書とは全く対応してなかった。田中先生が湯川先生を神様のように崇めていたのを覚えている。基本的な概念だけ徹底的に説明してものすごいスピードで進んでいく講義だったので,該当箇所を勉強するのに必死だった。標準的な本だとは思うが当時は大変苦労した記憶がある。記述がわかりにくいところがあるけれども,細かな計算も丁寧にしてあって今は重宝している。そういえば,名古屋大学でも一時期指定教科書であった。
桜井純「現代の量子力学」
この本を初めて読んだのは名古屋大学に着任した1年目のことであり,まだ日本語訳が出ていなかった。素粒子理論の学生のセミナーを担当することになりその指定教科書になっていた。読んでみて「とにかく感動」したことを覚えている。シッフでごちゃごちゃしていたことがすっきりまとめられていて量子力学の整理をするのに非常に役に立つ。基礎の量子力学を一通り学んだ後で読むと「量子力学ってこんなに見通しの良いもの?」と錯覚する本。
小出昭一郎「量子力学 Ⅰ,Ⅱ」
大学に入ってセミナーで使うというので読み始めた本。量子力学の考え方を丁寧に説明している。流れとしてはやや個性的なことがあるが,標準的な量子力学の内容をほぼ網羅している。特にIIは薄い本でありながら,固体物理に必要な量子力学がすべて尽くされている。これをマスターしていれば固体物理学に進めるであろう。
岡崎誠「量子力学演習」
お目にかかったことはないが物性理論の大家による良質な演習書。量子力学の美しい世界も必要であるが,いまや量子力学は産業の基盤と言ってもいいくらい重要なものである。そのためには「使える」量子力学が必要であり,実際に使う上で必要な事項を必要十分な簡潔した表現でまとめることが望まれる。この演習書のまとめも秀逸である。小出昭一郎の教科書と併せて読めば,物性物理学に必要な量子力学は身に付くであろう。学生ならば,1年間講義を受講しながらその流れに併せて,この演習書を全て勉強すれば確実に力がつくことは保証する。友達と勉強会などを開いて,発表し合ったりするといいかもしれない。この演習書をマスターしていれば,桜井やシッフはすいすいと読める。
原康夫「量子力学」
あまり真剣に読んでないが,量子力学の主要な点をうまくまとめてある。初学者向け。
メシア「量子力学 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ」
大変丁寧だと定評のある本。角運動量の合成のところだけ目を通しただけでほとんど読んでいないが,たしかにこの本を読めば量子力学はもういいかなという感じがする。シッフと同様標準的な本。
朝永振一郎「量子力学 Ⅰ,Ⅱ」
この本はすごい本である。生まれてきてこういう本に巡り会えたことをただただ感謝するばかりである。
固体物理学
キッテル「固体物理学入門」
固体物理を学んだ人でキッテルを知らない人はもぐりだと言われるくらい大変有名な本。初版は1953年で8版は2005年だから,50年以上も改訂され続けている。Wikipediaによるとキッテルは1916年生まれであるから,初版を出したときが37歳。8版を出したときが89歳で,今は99歳ということになる。ギネス級に息の長い教科書である。
どの版のキッテルを学んだかで世代がわかる。私が学んだのは第5版であった。大学3年生のときに英語版で毛利信男先生(日本で最初の宇宙飛行士毛利衛さんのお兄さん)の指導で学んだ。カンニング用に日本語版も購入した。このときはハードカバーであった。版の変更は普通の書籍はそれほど変化は大きくないと思うが,キッテルは劇的に変化することがある。私の学んだ5版は最悪であった。少し上の先輩が持っていた4版からは随分分量が減少していた。確かに,5版の訳者の序文にスリム化されたと書いてあるが,実は重要なことを相当に削ってあり,先輩や先生からそんなことも知らないのか,と何度も言われたことを思い出す。ゆとり教育みたいなものか。その反省からか,6版は再び,重要なことを取り入れて,重要なことをほぼ網羅することになった。7版は基本的には6版と変わりはない。2005年に出た8版は最近の物理を付け加えたほか,それまで引用されていた文献などが削除された。これはインターネットの普及などでもう必要あるまい,ということなのかもしれない。そして,日本語の訳がなぜか悪くなってしまっている。私の大学時代の指導教員の都先生によると,キッテルは2版が良いという。私が大学時代はまだreprintが手に入ったが今は手に入らない。つい最近大学の図書館で2版を借りてきて目を通してみたが,大変に記述が丁寧である。私の希望としては,今までの全ての版の良いところを取り入れた9版が出版されることであるが,それは難しいかもしれないので私家版キッテル固体物理学X版を密かに作っている(2〜8版のよいところ+独自の補足)。6版以降で優れているのは付録。これはどれもほとんどとびがなく重要なことを簡潔に説明している。また,問題に非常に重要なことが隠されていることが多い。普通の教科書では問題は本文の理解を深めるためにあるのだが,キッテルでは昔本文に入れていた内容を問題に入れていることが結構ある。もちろん理解を確認する問題もあるけれども。そういうわけで,キッテルを読むときは本文以上に付録や問題に目を向けてほしい。
キッテルもすごいが,訳者もすごい。翻訳は第2版から4人の著名な物理学者で始まったが,8版で訳者が一人増えたものの他の4人の訳者はそのままで,これもギネス級にすごいことである。ただ,ときどき気になる訳文はある。
キッテルの本が有名なのは確かであるが,いい本かどうかについては意見が分かれるかもしれない。私は「いい本」という立場の人間であるが,決して初学者にわかりやすいという風には思っていない。それは,固体物理のあらゆる分野を1冊の本に詰め込んだのだから,記述が簡略になるために仕方がないことなのかもしれない。固体物理を学ぶための前提がある程度必要になることと,行間が多いことなどがあげられるであろう。キッテルを読んでもわからない場合,記述不足のことが時々あるので,自分は勉強が足りないといって嘆く必要はないと思う。
キッテルは私の研究に極めて重要なRKKY相互作用に2番目の文字のKの人である。教育者としても有名らしく,バークレー物理学コース「力学」の著者でもある。キッテルの教科書のすごさは固体物理よりも「熱物理学」を読むといいかもしれない。この本は普通の熱力学と異なり,固体物理学を学ぶ基礎としての熱物理学を展開している。「熱物理学」は大学時代の熱力学の教科書であったが,今読み直すとそのすごさが実感できる。一読を勧める。キッテルの「固体物理学」で秀逸なのは付録である。これは,それぞれ重要なことは極めてエレガントにまとめてあり,式の省略もあまりない。
磁性物理学
私が所有している磁性の教科書を列挙すると次のようになる。最近出ている本についてフォローしていないが,ほぼ物理学としての磁性は網羅していると思う。
「物質の電気分極と磁性」1931 ヴァン・ブレック吉岡書店
「磁性の理論」1968 アンドレ・エルパン講談社
「磁性」1969 金森順次郎 培風館
「磁性I」1972 芳田奎朝倉書店
「磁性II」1972 芳田奎朝倉書店
「金属電子論」1983 近藤淳裳華房
「磁性の理論」1987 永宮健夫 吉岡書店
「近藤効果とは何か」1990 芳田奎丸善
「化合物磁性-局在スピン系-」1996安達健五 裳華房
「化合物磁性-遍歴電子系-」1996安達健五 裳華房
「重い電子系の物理」1998 上田和夫,大貫惇睦裳華房
「重い電子とは何か」2002 三宅和正 岩波書店
「固体の電子状態と磁性」2003望月和子/鈴木直 大学教育出版
「磁性入門」2007 志賀正幸 内田老鶴圃
「磁性I」2008 久保 健,田中秀数 朝倉書店
「磁性入門」2011 上田和夫 裳華房
「遍歴磁性とスピンのゆらぎ」2012高橋慶紀,吉村一良内田老鶴圃
ヴァンブレックの教科書とその次の教科書に出版の大きな開きがあるのは理由があるらしい。ヴァンブレックの教科書の出来があまりに良かったために,教科書を書こうという人が現れなかったということであった。しかし,30年もたつとさすがに内容が古くなり,新しい教科書が出始めた。数年前に大阪の古書店街でみつけて購入して少し読んでみたところ,確かにすごい。量子力学が完成したばかりで,量子力学の適用としての磁性を考えているので,量子力学と磁性の接続が明快である。最近の教科書で省略されている計算が丁寧になされているが,簡単に読みこなせる本ではないかもしれない。エルパンの本は大変丁寧な本で,ヴァンブレックの解説本のような感じであり,応用面も充実している。
私が学生の頃に磁性研究を行う者は4年生で金森を読んで,修士で芳田奎を読むというのが普通であった。
私が学んだ先生は「金森は基本で易しい本」とおっしゃっていたが,私自身は簡単な本ではないと思っていたがわかりやすい本ではある。新しい磁性の考えで書かれてその内容も高度なものなので,行間も含めて理解すれば少なくとも実験物理の研究者としては十分に通用すると思う。文章の端々にヴァンブレックの本の影響が見られる。近藤効果が解決される前の出版であるが,近藤効果についてもその本質が明確に書かれており,金森先生が第一級の物理学者であるということがよくわかる本である。誤植がほとんどないすごい本。金森先生は遠くからお姿を拝見したことがある。
芳田先生の教科書はとにかく難しい。何が難しいかというと,第二量子化の手法がいきなり出てきたりして,量子力学や場の量子論をある程度勉強していないと読めないと思う。物理数学の知識も必要である。未だにわからない箇所が実は沢山ある。この本を読むと,磁性は難しいと思ってしまう。間違いはほとんどないが,わからなくなる。散乱問題についてもかなり詳しく解説しているが,これは量子力学の散乱問題のまとめなのでそもそも散乱問題を勉強したことのない人には難しい。芳田先生のこの教科書を難しいと感じた人は確実に量子力学などの基礎物理学の理解が十分でないので,勉強し直した方が近道である。水準としては桜井やシッフ,メシア程度に加えて,桜井やザイマンの上級コースの量子力学もある程度わかっていた方がいい。芳田先生の集中講義を2回受けたことがある。物理学はやはり哲学だと痛感した記憶がある。
近藤先生の金属電子論は近藤効果の解説本。4章までは固体電子論の解説で,他の教科書でも書かれていることであるが記述が丁寧。5章以降が近藤効果の解説になる。近藤効果の解説をしているのに近藤効果という言葉が一言も出てこないという日本人らしい奥ゆかしい本。近藤先生のお人柄であろう。近藤先生の集中講義を受けたことがあるが本当に控えめであろ真面目な先生だと感じた。近藤先生に是非ノーベル賞をと思っているのは私だけではないはずである。
永宮先生の磁性の理論は永宮先生に関係する磁性のトピックを丁寧に解説したものであり,途中の式の計算の省略がほとんどなく丁寧な本である。しかし,磁性の全体像を理解することは難しいと思う。永宮先生は私の指導教官だった都先生が阪大にいたときの理論の先生で,雲の上の存在だと言われていた。すごいオーラを発していたということであるが,お目にかかったことはない。私にとっては,雲の上というよりむしろ歴史上の存在である。
「近藤効果とは何か」というのは芳田先生によって書かれた近藤効果の一般向けの解説本であるが難しい式(ポイントとなる式である)がどんどん出てきて,一般の人がにはかなり難しいのではないかと思う。一通り,近藤効果を勉強した人が自分の頭を整理するのにはいいかもしれない。
安達先生の磁性の教科書は実験屋に丁寧な本。安達先生は私が名古屋大学に着任したとき,その研究室の教授だった。そういえば,そのころこの教科書の原稿を一生懸命書いておられた。すべての磁性の分野を網羅しているだけに,間違いが多い本。間違いを訂正しながら読むといい勉強になるが,基礎力がない場合はどこが間違っているかわからなくて途中で挫折してしまうかもしれない。
重い電子系の物理は,重い電子系の理論と実験の第一人者が書き下した本である。この本についてのコメントは差し控えたい。
望月先生の教科書は金森先生の解説本という感じであり,記述が大変に丁寧である。望月先生の量子物理学と併せて読むといいと思う。
志賀先生の磁性入門という教科書には驚いた。磁性の教科書はどれも難しいという先入観があったが,志賀先生はそれをわかりやすく展開し,しかもかなりの水準のところまで持っていく。磁性物理とは何かということを知りたいと思えば,まずこれで勉強して,それから本格的な本に進めばいいのではないだろうか。
上田先生の教科書を通読して思うことは想像していた以上に手強い教科書だと言うことである。上田先生を初めて拝見したのは私がM1のときに富山大学で開催された物理学会のシンポジウムであった。若手のホープのような感じで大変エレガントに話されていたのを覚えている。もちろんそのときの内容は全くわからなかったのだが,上田先生の印象としてはダンディーでかっこいいというものだった。それ以降,何度も上田先生のお話をお聞きすることがあったが,その初期の印象通り大変に論理展開が明快で筋が通っていて,わかったような気にさせてくれる。何度かお話をしたことはあるが,おそらく上田先生は覚えていないことであろう。なぜこんな思い出話をしたかというと,この教科書は上田先生そのものでかっこいいのである。最初は,薄っぺらい教科書なので半期の講義で全部終わるだろうと思っていたのだが,そうはいかないことがわかった。かなり難しいことも,あっさりと書かれてあり,かっこ良くてダンディーな上田先生そのものである。磁性入門と謳っているものの,本当に磁性を最初から勉強しようと思って,この本を読もうとしたらかなり大変だと思う。一見,易しそうに書かれている部分でも最先端の物理からの視点で書かれており,奥は深い。この本を読むには,少なくともキッテルの磁性の部分は理解している必要があるし,解析力学,量子力学はある程度わかっていた方がいい。そして実際に読むときは,上田先生が相当に参考にされたと思われる金森先生の教科書を参考にしながら読むといいであろう。磁性のごたごたした部分は思い切って切り捨てて重要な点にしぼって,そこに関しては重要な概念を極めて適切な言葉でまとめあげている。私ならもう少し詳しく書くと思うが,そうすると教科書の分量が多くなるだけでなく上田先生のかっこよさが失われることになる。磁性入門ということになっているが,物理系大学院生向けの磁性入門なんだろうな。いずれにしても,この教科書が3000円もしないというのは大変にお買い得である。
遍歴磁性についての教科書は少なかったが,高橋先生が書いてくださった。じっくり腰を落ち着けて読みたいと思っているが,なかなか時間が取れない。高橋先生は遍歴電子理論の第一人者で,人物としても超一流。
何か一冊読むとすれば,金森先生の教科書だろうな。
物理学史
広重徹「物理学史」
これ一冊(Ⅰ,Ⅱで二冊)あれば何もいらない。広重先生は大変残念なことに早逝されている。私は直接にも間接にも面識はないが,この本の特徴は序文にある次の一文でよくわかる。
「可能な限り原典にあたり,原典にまで手の及ばなかったものは信頼のおける研究書・論文に依拠して,すべての叙述を確実となる史実に基づかせるよう努力した」
私が知っているつもりになっていた物理学史には伝承や思い違いが相当にあったことに気づかされた。物理学史はその当時の最高の頭脳における最先端の研究の極みであることが伝わってくる本。
朝永振一郎「物理学とは何だろうか」
朝永先生の遺作。古代の自然哲学から量子力学が始まるまでの物理の歴史を辿りながら,物理学がいかに作られていったかを語る本。朝永先生のやわらかい語り口により,物理の面白さが伝わる素晴らしい本。この本を読んでわかることは,物理学は決して頭脳明晰の天才たちだけで組み立てられてきたわけではなく,実に色々な人で出来上がってきたことである。むしろ,やや鈍な人間がすごい仕事をすることの方が多かったりする。しかし共通するものが一つだけある。それは努力を惜しまないこと。ただ当事者にとっては努力と思っていないのかもしれない。スポーツ選手が朝から晩までトレーニングをやることを苦に思わない?ことと似ているのかもしれない。ただ,趣味的な気持ちだけでは研究は出来ないので,当然辛いことは沢山ある。しかし実はその辛いことから新しい発見が現れるのである。人生っていいものだなあということが物理を通じてわかる本。文系の人にも是非読んでもらいたい本である。「自然科学の歴史」の講義の参考図書に指定している。